
抹茶アイス、抹茶ケーキ、抹茶ラテなどなど、抹茶のお菓子、飲み物に目がない人も多いであろう。一昔前には、「green tea」と訳されていた抹茶であるが、今では「matcha」と言えば、世界中で通じるほど、抹茶は世界中の人々に知られるようになった。健康志向も手伝って、いろんな国で抹茶ブームが起こり、今やその人気は安定の地位を保っている。しかし、抹茶好きな人でも、抹茶そのものを味わう薄茶(お薄)を飲んだことがないという人は結構いるかもしれない。抹茶を点てて飲む儀式である「茶道」は、古くから伝わる日本の伝統文化の一つであり、今も趣味や習い事とて人々に嗜まれながら受け継がれている。
應該有許多人對抹茶冰淇淋、抹茶蛋糕、抹茶拿鐵等抹茶甜點、飲料毫無抵抗力吧。抹茶過去被翻譯成「green tea」,但現在只要說「matcha」就能在世界上通用,抹茶已經廣為全世界的人所知了。在健康取向推波助瀾下,許多國家掀起抹茶旋風,現在其受歡迎程度維持著安定地位。但是,即使喜歡抹茶,應該也有許多人沒有喝過直接品味抹茶的薄茶(淡茶)吧。「茶道」為點抹茶(以茶筅刷抹茶)後飲用的儀式,是日本自古流傳至今的傳統文化之一,現在也被人們當作興趣或是才藝,領略這項素養的同時也傳承下去。
平安時代に中国の唐から伝わってきた茶は、最初は薬として飲まれていたが、鎌倉時代に禅宗の一派である臨済宗の開祖栄西が茶の種を植え始め、それが京都の方にまで広がって武士階級にもお茶を飲む文化が広まったといわれている。当時はお茶を飲み、その銘柄を当てる「闘茶」という賭け事が流行したが、安土桃山時代になると村田珠光は茶会での賭け事や飲酒を禁止し、客人との精神交流を重視するように説いた。それを受け継いだ武野紹鴎、そしてその弟子である千利休によって茶室、茶道具、作法が一体となった「茶の湯」が完家、裏千家、武者の小路千家」の流派が門弟をまとめる役割を担い、現在もこの「三千家」をはじめ、多くの流派によって茶道の文化が継承されている。
平安時代從中國傳來的茶,一開始是被當成藥品飲用,但在鐮倉時代,禪宗一派的臨濟宗開祖榮西開始種植茶葉種子,這還傳到京都,飲茶文化也在武士階級中普及。當時還流行品茶後,猜出茶葉品牌的「鬥茶」賭博,進入安土桃山時代後,村田珠光宣揚禁止在茶會中賭博以及飲酒、要重視與客人間的精神交流。繼承這點的武野紹鷗以及其弟子千利休完成了將茶室、茶道具、禮儀融為一體的「茶之湯」。之後在江戶時代,普及到大眾階級「表千家、裏千家、武者小路千家」等流派負擔統整門徒的任務,現在除了這「三千家」之外,還有許多流派繼承茶道文化。
日本のお寺に行くと、抹茶が飲める席を見ることも少なくない。抹茶を飲みながら庭園を鑑賞するなどという優雅なことをしてみたいと思いながらも、抹茶を飲むマナーが分からないために躊躇してしまう人も多いのではないだろうか。正式な茶会では細かい決まり事があるが、このような一般向けの場では作法を気にせずに気軽 に楽しめばよいとされている。それでも気になる人とは、
① お菓子はお茶が出される前に全部食べる。
② 茶碗は両手で持ち、左手の掌に載せる。
③ 茶碗の正面から飲まない。
到日本的寺院去,常見可以飲用抹茶的空間。應該有不少人想要優雅地邊飲用抹茶,邊欣賞庭院風光,但因為不知道飲用抹茶的規矩,所以躊躇不已吧。正式的茶會中有許多繁瑣規矩,但這類以一般民眾為對象的地方,可以不需要在意禮儀,輕鬆樂在其中即可。即使如此還是很在意的人,只要注意以下三點:
①甜點要在端上茶前食用完畢。
②雙手拿起茶碗後,擺在左手掌心上。
③不要就著茶碗正面飲用。
この三つの作法さえ気をつけていれば問題ないだろう。抹茶といえば一般的に茶筅で泡立てて作られる薄茶が知られているが、正式な茶事では、たくさんの抹茶を練るように作る濃茶も出される。薄茶の三倍の量を使う濃茶は、渋みのある抹茶を使うことができないため、より甘みのある高級な抹茶が使用される。ところで、抹茶に使われている抹葉は普通の緑茶と何が違うか疑問に思ったことはないだろうか。抹茶は直射日光を遮る方法で栽培された「碾茶」という緑茶を挽いたものであり、日に当たらずに育った茶っ葉は薄くて柔らかく、また色も鮮やかであり、苦みが少すなく甘みを感じるのが特徴である。製造工程に手間暇がかかっているため、値段も普通の緑茶より高額である。
如此一來就不會有問題了。說到抹茶,一般廣為所知的應該是用茶筅刷出泡沫來的薄茶,但在正式的茶會中,也會拿出使用大量抹茶攪拌出來的濃茶。使用薄茶三倍分量製作的濃茶,因為無法使用帶有澀味的抹茶,所以會使用更甘甜的高級抹茶。說到這裡,大家是否有過「抹茶使用的茶葉和普通綠茶有什麼不同」的疑問呢?抹茶是使用遮蔽日光直射栽培出的「碾茶」這種綠茶碾磨而成,遮蔽日光長大的茶葉薄又柔軟、且色彩鮮艷,苦味少帶有甘甜是其特徵。因為製造過程相當費時費工,價格也比一般綠茶高。
茶道は簡単に言えば亭主が客を招き、お茶を点ててもてなす儀式であるが、総合芸術とも言われている茶道は奥が深く、茶室や庭などの空間、茶道具や茶室に飾る掛け軸などの工芸品、茶会で出てくる懐石料理や和菓子といった食、客人をもてなす作法、四季折々の自然、また侘び寂びの哲学など、日本の様々な文化が内包されて発展したものであり、茶道を本当に理解するためには様々な面での教養が必要となる。少しでも茶道に興味を持った人は、二○一八年十月に公開された『日日是好日―お茶が教えてくれた15のしあわせ』を見てみてはどうだろうか。大学生の時に母の勧めで茶道教室に通うようになった主人公が二十五年の日々を振り返り、茶道から「生き方」を学んでいくというストーリーであり、映画の中ではお茶の点て方や作法を見ることができる。また、この映画の原作となった森下典子のエッセイを読んでみるのもいいだろう。
茶道,簡單來說就是主人邀請客人前來,點茶招待客人的儀式,但被稱為綜合藝術的茶道相當深奧,茶室及庭院等空間、茶道具及掛茶室內的掛軸等工藝品、茶會中端出來的懷石料理及和菓子等食物、招待客人的禮儀、四季時令的對應、以及侘寂哲學等等,是將日本各種文化內包其中,進一步發展的文化,想要真正理解茶道,就需要擁有各方面的教養。稍微對茶道有點興趣的人,不妨觀賞二○一八年十月上映的〈日日好日:茶道教我的幸福15味〉。(台灣於二○一九年二月上映)這是描述大學時在母親推薦下到茶道教室學習的主角回顧自己二十五年的每一天,從茶道學習「人生價值觀」的故事,在電影中可以看到刷茶方法以及禮儀。另外,也可以閱讀電影原著,森下典子所著的隨筆集。
「一期一会」という言葉を聞いたことがあるだろうか。実はこの言葉は茶道由来のものであり、「どの茶会でもその機会は二度と繰返されることはなく、生涯に一度しかない出会であると心得て主客ともに誠意を尽くすべきである」という意味から「もしかすると二度とは会えないかもしれないという覚悟で人に接しなさい」という戒めも含まれている。日本のおもてなし文化というのは、実は人に精神誠意を尽くしてもてなすという茶道の神髄が根本となっている。
是否曾聽過「一期一會」這句話呢?其實這句話由來自茶道,從「不管是哪場茶會,都不可能再有第二次相同機會,要把這是生涯僅此一次的相逢放在心上,主客皆需克盡所有誠意」的意思中,也有「要抱著或許再也沒第二次見面機會的覺悟待人接物」的教訓。日本無微不至的殷勤款待文化,其實其根本就是對人奉獻精神誠意、盛情款待的茶道精髓吧。
*文章源自 EZ Japan <Nippon 日本傳統趣味玩賞>
你可能有興趣
嚴選課程試看影片
所有留言

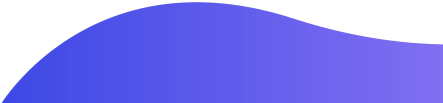

 使用Google登入
使用Google登入